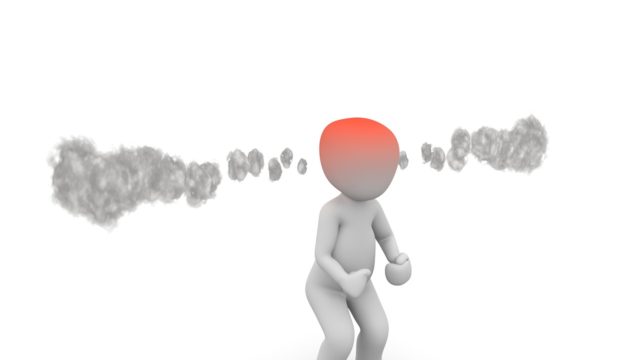半年以上の育休取得を予定しているヨシヒロです。こんにちは。
あなたは子育て、子どもの教育の方針みたいなもの、自分の中に持っていますか?
僕は子どもの頃、僕がやりたいように何でも放っておいてやらせてくれた(でも遠くから見てくれていた)母親と、「あれはやめたほうがいい、こうしたほうがいい」と指導するタイプの父親の間で育ちました。
中学へ上がる頃に両親は離婚し、それ以降は母の元で育ったので、僕は母親の教育方針によって、割とやりたいことをやりたいようにやってきた学生だったと思います。
そんな影響かどうかはわかりませんが、子どもには好きなように、様々な経験を自由にさせてあげたいと思っています。失敗しそうなことも成功しそうなことも。
そんなことを考えたとき、親は子どものやることにどこまで手を出すのか?という判断をちょいちょい迫られることになりそうです。
子どものやりたいようにやらせると言っても、子どもが他人を傷付けたり明らかにやってはいけないことをしているのを傍観するわけにはいきません。
今回はそんな「親がどこまで手を出すべきか」という線引きの仕方について書いてみます。実例もいくつか挙げましたので、参考にしていただければと思います!
目次
親が手を出すべき4つの判断基準
正直言って、どこまで親が手を出すべきなのか?人を傷つけたり法を侵したりしそうなときかなぁ?なんて漠然と考えていたとき、こんな記事に出会いました。
子育てにも部下育てにも使える、黄金の4つの指標
シバタナオキ氏 「決算が読めるようになるノート」より(business insiderへの転載記事)
この記事によると、親が解決すべき問題か、子どもが自ら解決すべき問題か、その線引きは難しいとしながらも以下のような基準が提示されています。
1. 誰かが怪我をする(可能性が高い)
2. 誰かの持ち物が無くなる(可能性が高い)
3. 親(上司)の人権が侵害される
4. 子供(部下)が問題を自分で解決するには幼すぎる(経験やスキルが足りない)
(子育てにも部下育てにも使える、黄金の4つの指標記事より引用)
この4つの質問に1つでもYESと答えなければならない問題なら、それは親が解決すべき問題だと書かれています。
ちなみに親を上司、子どもを部下と読み替えればビジネスシーンにも当てはまるのだとか。そりゃそうかもしれないね。
この記事の中では小学生の子どもが宿題を忘れた時は子どもの責任(だから親は届けない)、2歳の子どもが牛乳をこぼした時の後始末は親がやるべき、と言った事例が挙げられています。
ふむふむ・・・なるほど。確かにこういった指標を定めて、それに従って判断することで、一貫した判断ができそうな気がします。
1歳半の子どものやることにどこまで手を出すか
僕はもうすぐ1歳半の息子がいますので、それくらいの子どもの場合に、親がどこまで手を出すべきか?この4つの基準でいくつか事例を考えてみます。
子どもが走り回ってこけたとき
個人差はありますが、1歳くらいになれば子どもは歩き回るようになります。1歳半にもなれば、小走りであちこち動き回るようになります。
そんな子どもが走り回って転んだとき、優しいパパはついついすぐに手を差し伸べてしまいそうですが、これはどうでしょうか?
誰かが怪我をする(可能性が高い)かどうか。この判断基準に照らすと、こけた子ども本人は小さな擦り傷くらいは作るかもしれませんが、怪我というほどのものでもないように僕は思います。
こけたら立ち上がる。そして手や服をパンパンと払う。それくらいはできる子になって欲しいので、僕はすぐには手を差し伸べずに、
と子どもに声をかけます。「痛いの痛いの・・・」とここまで言ったところで、子どもが「飛んでった」と笑顔で自分で言っています(笑)
もう歩けるし、走れるんだから、こけたのは自分の責任。そう考えればいいのかなと思います。
ただし、例えばちょっと高いところや交通量の多い道路など、こけたらそのあと擦り傷では済まなさそうな場合は、これは親の責任です。
こけたらすぐさま抱き上げて移動するか、あるいはこけないように手を引く、抱っこするなど、親が手を差し伸べるべきですね。
そうやって一貫した判断をしてあげれば、車が多い道では手を繋ぐんだとか、子どもも理解するようになってくると思います。
スーパーに陳列されている物を勝手に持ってきたとき
次はスーパーに買い物に行ったとき、陳列棚に置いてある商品を子どもが勝手に持ってきた場合はどうでしょう?持ってきた商品は特に買う必要がないものだとします。
買うつもりがないものですから、当然もとの棚に返すのが常識ですね。でも子どもにはそんなことはわからない。
誰かの持ち物がなくなる(可能性が高い)という判断基準に照らせば、商品はお金を払うまではお店の物ですから、子どもが勝手に持って帰ってしまったらそれはダメなのはわかりますね。
だからこの時は、「これは買わないからここに置いておくんだよ。」と子どもを諭し、親が陳列棚に商品を返却するのがいいのかなと思います。(当たり前の話ですが)
もし購入予定のものであるなら、そのまま子どもに持たせておいてもいいかもしれませんが、「レジでピッてやってもらうんだよ」と、その時には手放させる習慣をつけたほうが良さそうです。
子どもが親の鼻の穴に指を突っ込んでくるとき
育児日記にも書きましたが、うちの息子はなぜか妻や僕の鼻の穴に指を突っ込んでくるのが好きです。布団に入ってうつろうつろしている時も、半分無意識(?)に指を突っ込んできます。

これは親の人権が侵害されることに当たるでしょうか?僕もそうですが、ほとんどの親はこれを人権侵害とは思わないですよね。相手は1歳半の子どもですから。
これが例えば小・中学生で、明らかに相手を侮辱するような、いじめるような行為だとわかっていながらやっているのだとすれば、それは人権侵害ともとれるかもしれません。
年齢によっても判断が変わってくるということですね。とりあえず1歳半の今は、親は「おかしなことする子ね」と思う程度ですので、ほおっておけばいいかなと。
プラレールの電車がひっくり返ってしまったとき
では最後に、プラレールの電車で遊んでいる1歳半の息子が、電車のおもちゃがひっくり返ってしまった時にうまくいかなかったとすねて泣いています。
この時、子どもが問題を自分で解決するには幼すぎる(経験やスキルが足りない)かどうかの判断基準に照らしてみると、親がひっくり返った電車を直してあげるべきでしょうか?
これも親によって判断が分かれそうな問題ですが、僕の答えは「できるだけNo」で、なるべく自分で直せるようになってほしいと思います。
プラレールは青い線路と実際の電車をモチーフにしたモーターで動く電車のおもちゃですが、対象年齢は確か3歳くらいから?だった気がします。
そういう意味では、1歳半の息子が遊ぶにはちょっと早いのかもしれませんが、おばあちゃんに買ってもらって以来、やけに気に入って毎日結構な時間、プラレールで遊んでいます。
対象年齢的には合っていないのかもしれないけど、それだけハマって毎日遊んでるなら、十分に経験はあると判断しても良いかと思いました。
だから、「電車がひっくり返ったらこうするんだよ。」と根気よく教え、子どもが自分で直せるようになるように、最初だけ手を差し伸べることにしています。
まぁ、1歳半の子どもの遊び方は荒っぽいので、電車はすぐにひっくり返るんですが、その度に親が直してあげなきゃいけないのも結構大変なので・・・というのも正直なところですかね。
おわりに
ということで、どんな時に親は子どもを手助けすべきか?自分なりに整理してみました。
上の事例は全てうちの息子のことなのですが、何か一貫性を持って判断する基準を持つことはやっぱり大事だなと改めて思いました。
親の意見がコロコロ変わっていては、子どももどうしていいか分からなくなりますからね。
なるべく手を出さないで子どもに経験させたい、でも要所ではサポートしてあげなきゃいけない。我ながら難しい教育方針だなと思いました。
何でもかんでもサポートしてあげるという、過保護な方針も一方ではありますけどね。それが悪いとは言いませんが、僕は選ばない方法です。
あなたはどんな教育方針で行きますか?
最後まで読んでいただきありがとうございました。